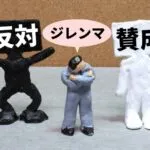モバイルバッテリーが膨らんでしまったとき、「これって危ないの?」「どうやって捨てたらいいの?」と、不安になったり迷ってしまう方も多いと思います。
特に普段あまり意識しないアイテムだからこそ、いざというときに正しい知識がないと戸惑ってしまいますよね。
この記事では、そんな不安を解消するために、膨張したモバイルバッテリーがなぜ危険なのか、どのような処分方法が安全なのか、また保管時の注意点や、環境にやさしいリサイクル方法まで、わかりやすく紹介していきます。
さらに、実際の事故例や処分前に確認すべきポイントなども詳しく取り上げ、「知らなかった!」では済まされない大切な情報をまとめました。
この記事を通して、安心・安全な行動につなげていただけたら嬉しいです。
膨らんだモバイルバッテリーの危険性

あなたも膨らんできたモバイルバッテリーを持っていませんか?
「使えているからいいや!」 そう思っているかもしれません。
でも、それっていつも危険を持ち歩いているという事をしっかり認識しておかないと非常にマズいんです。
先ずは、膨らんだモバイルバッテリーの危険性について見て行きましょう。
<PR>
安全性の高いモバイルバッテリーって無いの?
実は有るんです!
心配しながらモバイルバッテリーを使う生活からサヨナラしたいなら…
膨張の原因とそのリスク
モバイルバッテリーが膨らむ原因には、長時間の充電や高温環境での使用、劣化したバッテリーの継続使用などが挙げられます。
また、粗悪な製品や非純正の充電器を使っている場合も、内部の化学反応が異常をきたし、膨張の原因となることがあります。
特に、夏場の車内や直射日光の当たる場所に放置してしまうと、内部の温度が急上昇しやすく、バッテリーが膨張するリスクが高まります。
些細なことのように見えても、積み重なることで深刻な事態になってしまう可能性があります。
見た目が少し膨らんでいるだけでも、中では可燃性のガスが発生している可能性が高く、非常に危険な状態です。
そのまま放置したり、押さえつけて形を戻そうとする行為は絶対に避けましょう。
内部に圧力がかかることで破裂の危険性がさらに高まり、火災ややけどといった重大な事故につながる恐れがあります。
膨張を確認したら、使用を中止し、安全な場所での保管と早めの処分を心がけることが大切です。
発火や事故の可能性
膨らんだバッテリーを無理に使い続けると、内部の圧力がさらに高まり、発火や爆発のリスクがぐんと高まります。
バッテリーの中にはリチウムなどの可燃性物質が含まれており、それが空気と反応することで火花や炎が発生する可能性があるのです。
また、スマートフォンや電子機器に接続した状態で爆発が起きた場合、周囲の物を巻き込んで火事につながるケースもあります。
家の中で火災が起きると、家族やペットにまで危険が及ぶ可能性があるため、本当に怖いですよね。
もし手元に膨張したバッテリーがある場合は、使わずに静かな場所に置き、できるだけ速やかに処分の手続きをとることが、家族全員の安全を守る第一歩になります。
少しでも異常を感じたら、絶対にそのまま使わず、安全な場所で保管し、できるだけ早く適切に処分するようにしましょう。
実際に起きた火災・事故の事例
ニュースなどでも、バッテリーが爆発したという事故がたびたび報告されています。
中には、バッテリーが突然膨張し、発火してしまったというケースもあり、日常のちょっとした油断が大きな事故につながることもあるのです。
さらに、電車の中や公共施設でバッテリーの異常が原因で一時避難となる事態が起こったこともあります。
以下が事例の一部となります。
① 電車内で爆発し火災(2023年・東京メトロ千代田線)
東京メトロ千代田線の車内で、乗客が持っていたモバイルバッテリーが突然爆発。激しい煙が発生し、乗客が一時避難する騒動となりました。
原因は、劣化したバッテリーを使用していたことに加え、過充電による発熱が疑われています。
幸い大きなけがはありませんでしたが、駅での運行が一時停止されるなど大きな影響が出ました。
② 自宅の机の引き出しで発火(2022年・神奈川県川崎市)
使わなくなったモバイルバッテリーを机の引き出しに保管していたところ、ある日突然煙が出て火花が発生。
家具の一部が焦げる被害に。調査の結果、金属製の文房具と接触したことで端子がショートしたことが原因でした。
絶縁処理をしていなかったことが引火リスクを高めた典型的な事例です。
③ 車内放置で膨張 → 自宅内で爆発(2021年・大阪府堺市)
夏場に車内に放置され、膨張したモバイルバッテリーを自宅に持ち込んでそのまま放置していたところ、数日後に爆発し、壁が焦げるほどの被害に。
内部に溜まったガスが気温変化で圧力を高めたことが要因とされ、破裂の衝撃でガラスが割れるなど、重大な事故につながる寸前でした。
最近では、7月に東京の山手線(新大久保~新宿間)にて、乗客のバッグに入れてあったモバイルバッテリーが発火した事例が有りました。
所持していた女性が指をやけどし、他の乗客4名が打撲や足首の捻挫などを負ったとのことです。
また、列車は火災報知器が作動し非常停止措置が取られ、山手線を含むJR東日本エリアの列車運行が一時停止し、最大で2時間ほど遅延が発生しました。
このバッテリーはリコール対象製品であり、過去にも火災事故が複数報告されていたということです。
人混みの中でモバイルバッテリーの発火事故が起きれば、パニックや混乱を招くだけでなく、大勢に危害を及ぼす可能性が有る事が分かりますね。
モバイルバッテリーは小さくて便利な道具ですが、扱いを間違えると大きな事故につながる危険性もあるということを、常に頭に入れておくことが大切です。
<PR>
少しでも不安が有るのなら、一度説明を見てみませんか?
便利でも危険だったら意味がありませんよね!
処分前に確認すべきこと

保証期間中かどうか確認しよう
メーカーによっては、保証期間内であれば無償交換や回収をしてくれる場合もあります。
これは、製品の不具合や劣化によって発生した問題に対して、責任を持って対応してくれるというメーカー側の配慮です。
まずは、購入時のレシートや保証書を手元に用意して、製品の購入日や保証期間が記載されているかを確認してみてください。
さらに、保証内容に「膨張や故障時の無償交換」が含まれているかもチェックしておくと安心です。
製品によっては、「物理的破損は対象外」となっている場合もあるので、細かな条件にも目を通しておきましょう。
場合によっては、製品登録をしているとスムーズに対応してもらえることもあります。
たとえば、公式サイトでシリアルナンバーを登録しておくと、保証期間の確認やサポート窓口の利用が簡単になるケースもあります。
登録特典として延長保証がつくメーカーもあるため、日ごろからの管理がとても重要です。
このように、保証があるかないかを見極めるだけでも、処分方法が大きく変わってくるので確認はとても大切です。
きちんと調べておけば、無駄な出費を防げるだけでなく、安全に処分できる道も広がります。
メーカー回収サービスの有無をチェック
公式サイトなどで、回収サービスを行っていないか調べてみましょう。
特に大手メーカーでは、リチウムイオン電池のリサイクルを推進している場合が多く、環境への配慮とともに安全な回収を行っています。
無料で対応してくれるケースもあり、専用の問い合わせフォームやサポート窓口を通じて申請が可能です。
メーカーによっては、郵送での回収を受け付けている場合もあり、自宅から簡単に手続きできることもあります。
事前に回収キットが送られてくる場合や、ゆうパックなどで返送するだけの簡単な手続きもあるので、手間をかけずに安心して処分ができます。
このような郵送サービスは、忙しくて家電量販店に行けない方や、近くに回収ボックスが設置されていない地域にお住まいの方にもとても便利な方法です。
また、返送時の送料が無料の場合もあるため、処分にかかる負担が少ないのも嬉しいポイントですね。
データの有無・プライバシーリスクも意識
モバイルバッテリーにデータは入っていないことが多いですが、万が一のために処分前に仕様を確認しておくと安心です。
特に、最近ではスマホと連動して動作するタイプや、アプリと接続されるスマートバッテリーも登場しており、何らかの情報が本体に記録されているケースもゼロではありません。
また、スマートフォンとバッテリーが一体型になっているモバイルケースや、タブレットや音楽プレイヤーに内蔵されているタイプの製品もあります。
そのような場合、単なるバッテリーと思って処分してしまうと、機器に保存されていたデータが第三者に渡ってしまう恐れも考えられます。
特に、バッテリーと一体型になっている製品やスマホケース型のバッテリーなどは、機器のデータが残っていないか念のため確認しておきましょう。
万が一不安な場合は、事前に初期化を行ったり、専門のサポートに問い合わせて、安全な状態で処分することをおすすめします。
モバイルバッテリーの適切な処分法

自治体のルールを確認しよう
多くの自治体では、モバイルバッテリーを不燃ごみや可燃ごみとして出すことを禁止しています。
これは、バッテリーが持つ発火や爆発のリスクを回避するためであり、正しい処分ルールを守ることが自分自身や周囲の安全を守ることにもつながります。
まずは、お住まいの市区町村の公式サイトを確認し、どのような方法でバッテリーを回収しているのか、受付場所や受付日時なども含めてチェックしましょう。
地域によっては、定期的に小型家電リサイクル回収を行っているところもあります。
また、「充電式電池」「リチウムイオン電池」などのキーワードで検索すると、詳しい取り扱いルールが見つかりやすくなります。
加えて、環境省や家電リサイクル関連の公式ページでは、より広範なリサイクルの流れや注意点も掲載されていますので、必要に応じて参考にしてみるとよいでしょう。
このように、自治体ごとに異なるルールをしっかり把握しておくことで、安心・安全にバッテリーを処分することができます。
回収ボックスの利用方法
家電量販店やホームセンターなどに、バッテリー専用の回収ボックスが設置されていることがあります。
これは、一般のごみとして出せないバッテリーを安全に回収・処理するためのしくみで、環境にもやさしい取り組みの一つです。
回収ボックスは、店頭の目立つ場所や出入口付近などに置かれていることが多く、誰でも無料で利用できます。
持ち込む前には、必ず絶縁処理(テープで端子を覆う)をしてから持っていきましょう。
電気が流れないようにすることで、他のバッテリーとの接触による火花や発火を防ぐことができます。
ビニールテープや専用の絶縁テープを使うのがおすすめです。
また、使用済み電池やバッテリーを回収する「リサイクル協力店」のステッカーが貼られているお店を目印にすると安心です。
ステッカーには、グリーンのリサイクルマークが描かれており、一目で分かるようになっています。
なお、小型家電回収ボックスとは分かれている場合もあるので注意が必要です。
回収対象や設置場所が異なることがあるため、事前に店舗のスタッフに確認したり、店内の案内表示をよく見て判断するようにしましょう。
回収業者への依頼方法
大量に処分したい場合や、安全性を最優先にしたい方は、専門の回収業者に依頼するのがとても安心です。
特に、業務用やイベントで使われたモバイルバッテリーがたくさんある場合や、一般的な回収ボックスでは対応できないほどの数量があるときには、専門業者による対応が最適です。
回収業者はバッテリーの特性やリスクを熟知しているため、輸送や保管、処分における安全管理も徹底されています。
プロの手に任せることで、自分で処理する際に起こりうる火災や破損などのリスクを大幅に減らすことができます。
費用はかかる場合がありますが、安全性の高さと手間の少なさを考えれば、十分に価値のある選択肢と言えるでしょう。
事前に電話やメールで問い合わせをし、見積もりをとっておくと、処分費用や手続き内容を明確に把握でき、トラブルを防ぐことができます。
法人や店舗などでモバイルバッテリーを多く取り扱っている方はもちろん、個人でもまとめて処分したいときや、不安を感じる場合には、こうした業者の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
フリマアプリやリサイクルショップで売るのはNG?
膨張したバッテリーを誰かに譲ったり売ったりするのはとても危険です。
たとえ一見して異常が見えなくても、内部では化学反応が進行している可能性があり、いつ発火や爆発が起きても不思議ではありません。
フリマアプリやオークションサイトでの出品、知人へのお譲りなど、好意や不要品の有効活用のつもりであっても、思わぬ事故につながるリスクがあります。
特に、購入者が事情を知らずに使用してしまった場合、やけどや火災といった重大な事故につながる恐れもあります。
その責任が出品者側に問われるケースもあり、トラブルが大きくなってしまうことも考えられます。
壊れたものを出品してしまうと、相手がケガをしたり、購入者とトラブルになってしまう可能性もあります。
譲る気持ちはやさしくても、安全第一で考えましょう。
使えそうに見えても、少しでも異常が見られるバッテリーは「譲らず、売らず、安全に処分」が鉄則です。
膨らんだモバイルバッテリーの安全な保管方法
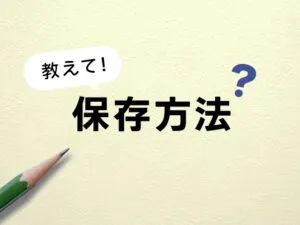
火の近くはNG!安全な保管場所とは?
高温・湿気の多い場所を避け、風通しの良い冷暗所に保管してください。
直射日光の当たらない、安定した温度を保てる場所が理想的です。
また、湿度が高すぎるとサビや腐食の原因になることもあるため、できれば除湿剤などを併用するとより安心です。
床に置く場合は、新聞紙や耐熱性のマットなどを下に敷いたうえで、金属製の箱や耐火素材の容器に入れておくのがおすすめです。
密閉容器に入れる場合は、適度に空気が通るような工夫もあると理想的です。
押し入れや車内などは温度が上がりやすいため避けましょう。
特に夏場の車内は数十度まで温度が上昇することがあり、膨張や発火のリスクが非常に高くなります。
玄関の靴箱やベランダの陰なども検討できますが、雨水や直射日光には十分注意してください。
屋外で保管する場合は、防水性・耐熱性のあるボックスを使用し、できるだけ室内の代替として使えるような安全な対策をとっておくと安心です。
絶縁テープを使った危険防止策
金属部分(端子)がむき出しのままだと発火の恐れがあります。
空気中の水分や金属との接触によって電流が流れ、思わぬ火花や発熱を引き起こす可能性があるため、とても危険です。
電気を通さない「絶縁テープ」で端子をしっかり覆うことで、このような事故を未然に防ぐことができます。
絶縁テープは、ホームセンターや100円ショップでも簡単に手に入ります。
黒色のビニールタイプが一般的で、伸縮性がありピタッと密着するのが特徴です。
貼る際には端子全体をしっかり覆うようにし、隙間ができないよう注意しましょう。
万が一落としてしまった場合でも、絶縁テープでしっかりカバーしておけば、他の金属やバッテリーと接触しても発火やショートのリスクを減らすことができます。
また、保管中に袋の中でこすれたりしても安心です。
ガムテープやセロハンテープでは絶縁効果が不十分なため、代用はせず、必ず専用の絶縁用テープを使用してください。
安全のために、小さな手間を惜しまないことが大切です。
破損した場合の応急処置と注意点
破損して液漏れしている場合は、絶対に素手で触らず、まずは火の気のない場所にそっと移動させましょう。
その際、バッテリーを動かすときに刺激を与えないよう、できるだけそっと扱うことが大切です。
液体が広がっている場合は、紙や布などで吸い取ろうとせず、直接手に触れないよう注意してください。
その上で、ジッパー付きの密閉袋や、チャック付きのビニール袋に入れて一時的に保管します。
さらに念のため、袋を金属製や耐熱素材の容器に入れておくと安心です。
そのまま放置せず、早めに専門業者や自治体に連絡を取り、正しい処分方法を確認してください。
素手で触れると皮膚に刺激を感じたり、目に入った場合は重篤な障害につながる可能性もあります。
バッテリー液は腐食性があり、わずかな量でも皮膚や粘膜にダメージを与える恐れがあります。
作業を行う際は、必ず厚手のゴム手袋やマスク、できれば保護メガネも着用して、安全を確保しましょう。
また、作業は必ず換気の良い場所で行い、作業後は手や顔をしっかり洗い流すことも忘れないでください。
環境に配慮したリサイクル方法

リサイクルの重要性とそのメリット
膨らんだモバイルバッテリーを適切に処分することは、自分自身の安全だけでなく、地球環境を守ることにもつながります。
リチウムなどの希少な資源は再利用が可能で、リサイクルすることで新しい製品の原材料として生まれ変わります。
ゴミとして焼却すれば有害物質が発生する恐れもあるため、リサイクルはとても大切な選択肢です。
最悪の場合、焼却施設に被害を及ぼす事も有るので一般ごみと一緒に廃棄することは厳に慎むようにしましょう。
リサイクルを通じて資源を有効活用することは、自然環境の保護にもつながります。
限りある資源を大切にし、未来の世代に負担を残さないためにも、ひとりひとりの意識が大切です。
モバイルバッテリーの回収対象とそのプロセス
回収の対象となるのは、家庭用の小型モバイルバッテリーが中心です。
リチウムイオン電池、ニッケル水素電池などが含まれます。
回収後は、専門の施設で安全に分解され、金属などが選別・再資源化されます。
多くの場合、絶縁処理を施した状態で回収ボックスへ持ち込むか、メーカーや自治体の指定に従って郵送する形になります。
どの種類のバッテリーが回収対象かは、事前に自治体またはメーカーの案内で確認しておくと安心です。
家庭でできるリサイクル活動
モバイルバッテリーの処分だけでなく、家庭でもできるリサイクル活動はたくさんあります。
不要になった家電の分別や、使い捨て乾電池の回収ボックス利用、家電量販店のリサイクルコーナーへの持ち込みなど、身近なところから始められます。
子どもと一緒に「なぜリサイクルが大切なのか」を学びながら取り組むことで、家庭の中でも環境意識が自然と高まっていきます。
日常のちょっとした工夫が、地球にやさしい行動につながりますよ。
電気屋で回収される仕組みとは?
家電量販店やホームセンターでは、一般家庭から出る使用済みのモバイルバッテリーや乾電池を回収する仕組みが整っています。
「小型充電式電池回収BOX」などが設置されており、誰でも無料で利用可能です。
これらの店舗は、JBRC(一般社団法人JBRC)という団体に加盟しており、適正なルートで回収から再資源化までが行われます。
回収ボックスの場所や対応店舗は、JBRCの公式サイトで地域検索ができるので、ぜひ活用してみてください。
モバイルバッテリー処分にまつわる誤解と注意点

不燃ごみとして捨てる危険性
モバイルバッテリーを「ただの電池」と思い、不燃ごみや可燃ごみに出してしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかしこれはとても危険な行為です。ごみ収集車の中で他のごみとぶつかったり圧縮されたりすると、発火や爆発の恐れがあります。
実際、回収時の火災事故の多くはバッテリーが原因となっているケースもあり、自治体でも強く注意を呼びかけています。
知らずに捨ててしまうことが、思わぬトラブルや被害を生むことになるため、必ず正しい方法で処分しましょう。
モバイルバッテリーと乾電池・充電池の違い
見た目が似ていても、モバイルバッテリーと乾電池・充電池はまったく異なるものです。
乾電池は使い切りの一次電池、モバイルバッテリーは繰り返し使えるリチウムイオン電池などが主流の二次電池で、発火のリスクも段違いです。
さらに、モバイルバッテリーには回路基板が組み込まれているものが多く、異常が起きた際にはその回路が過熱・発火の原因になることも。
見た目だけで判断せず、それぞれに適した処分ルールを守るようにしましょう。
分解・破棄・燃やす…絶対NGな処分法
「中身を見てみよう」とバッテリーを分解しようとしたり、「燃えるごみにしてしまえばいい」と思って燃やすのは、絶対にやめてください。
中には有害物質が含まれていることもあり、破損すれば化学反応で発熱・爆発を起こす危険があります。
特にドライバーやカッターで開封するような行為は非常に危険です。
安全に処分するためには、素人判断ではなく、専門的な回収ルートを利用することが何より大切です。
おすすめの回収場所と業者

ヤマダ電機での回収サービス
ヤマダ電機では、使用済みの小型充電式電池やモバイルバッテリーの回収を店頭で行っています。
店内に設置された「リサイクルBOX」に絶縁処理を施したうえで持ち込めば、無料で回収してくれるのでとても便利です。
また、ヤマダ電機はJBRC(一般社団法人JBRC)の協力店となっているため、安心して処分できます。
対象の電池や回収の詳細については、事前に最寄り店舗へ電話で確認しておくとスムーズです。
ノジマとの協力体制
ノジマ電機もまた、リチウムイオン電池やモバイルバッテリーの回収に積極的に取り組んでいる家電量販店の一つです。
ノジマは、地域の環境活動にも力を入れており、持ち込まれた電池はJBRCのルートで適切に処理されます。
受付カウンターにてスタッフへ声をかけることで、専用の回収ボックスへ案内してくれる店舗も多く、初心者にもわかりやすい対応が魅力です。
株式会社CIOのモバイルバッテリー回収サービス
株式会社CIOは、不要になったモバイルバッテリーの適正な処分や再資源化を推進する一環として、会員向けの回収サービスを実施しています。
JBRC(一般社団法人 小型充電式電池リサイクル推進協議会)にも加盟しており、環境配慮の姿勢を明確に示しています。
■ 対象製品
CIO製モバイルバッテリー:もちろん回収対象です。
他社製モバイルバッテリー:他社製品も回収対象になっており、より処分の選択肢が広がります。
本サービスは CIO会員限定 のサービスですが、会員登録は無料で、公式サイトから手続きができます。
仮申請:マイページにログインし、専用フォームから仮申請をして下さい。
URLは以下になります。
CIO製モバイルバッテリー:https://connectinternationalone.co.jp/collectservice/
他社製モバイルバッテリー:https://connectinternationalone.co.jp/othercollectservice/
本申請:回収希望日などを入力し申請完了後、専用の返送用封筒が発送されます。
返送:届いた返送封筒にモバイルバッテリー(本体のみ)を入れて郵送で返送。
なお、本サービスを利用すると、 回収特典としてクーポンがもらえます。
クーポンは、CIO公式Amazon店などで使える割引クーポンとなっています。
回収個数 割引率(CIO製) 割引率(他社製)
1個返送 10%OFF 2%OFF
2個返送 13%OFF 4%OFF
3個以上 15%OFF 6%OFF
■ 実際の利用者の声
ブログ投稿などによれば、フォーム入力から仮申請・本申請まで 10~15分ほどで完了し、手続きがスムーズ。
■ 注意点
会員登録と手続きは必要ですが、手順はシンプルでアクセスしやすい設計です。
返送できるのはバッテリー本体のみで、外箱・ケーブルなどの付属品は不可です。
量を多く送る場合は、封筒が複数届くこともあるため案内に従って対応しましょう。
CIOのモバイルバッテリー回収サービスは、手軽に、かつ環境配慮しながら不要バッテリーを処分できる魅力的な仕組みです。
割引クーポン付きで新製品への移行もスムーズという点が大きなメリットですね。
読者の方にもおすすめしやすい内容だと思います。
地域の回収施設の調べ方と利用方法
お住まいの自治体や地域によっては、定期的にリサイクル回収を行っている施設があります。
自治体の公式サイトや、環境省のリサイクルマップ(https://www.env.go.jp/recycle/)などを活用すれば、近くの回収場所を簡単に調べることができます。
地図検索で「小型家電 回収 ボックス」「充電池 回収 地域名」などのキーワードを使うと、該当施設が一覧で表示されるのでとても便利です。
持ち込み前に、回収可能な品目や注意事項をしっかり確認しておきましょう。
ちなみに、習志野市の場合は、モバイルバッテリーを含む小型充電式電池の廃棄に関する案内や担当窓口は、クリーンセンター クリーン推進課が所管しています。
以下がURLとなりますので確認してみて下さい。
習志野市公式ウェブサイト:https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kurin_suishin/index.html
習志野市では、モバイルバッテリーは「リチウムイオン電池」など充電式電池に該当し、有害ごみとして扱われます。
電化製品から取り外した状態で、有害ごみの日に出すのが基本です。
無料回収と有料回収の違い
モバイルバッテリーの回収には、無料のものと有料のものがあります。
家電量販店の回収BOXやメーカーによる郵送回収は基本的に無料ですが、量が多かったり、破損・液漏れしているバッテリーの場合は有料になるケースがあります。
また、法人・業務用途で使われたバッテリーは、事業系ごみ扱いとなり、専門業者による有料回収が必要になる場合があります。
無料で回収してもらえる条件を確認し、必要であれば事前に見積もりを取ることが安心です。
実際にあった体験談・失敗談

実際の処分方法を試した人の声
「最初はどうすればいいのかわからず不安だったけど、自治体のサイトで確認したら回収ボックスの場所が載っていて安心した」
「ヤマダ電機に持っていったら丁寧に案内してくれて、手続きも簡単だった」
など、多くの方が最初は迷いながらも、正しい手順で安全に処分できたという声が寄せられています。
特に女性や高齢の方からは、
「回収ボックスに入れるときに不安だったけど、絶縁テープでしっかり包んでから行けば安心」
「スタッフがやさしく対応してくれてありがたかった」
といった体験談も多く見られます。
火花が出た!? 危険な保管で起きたトラブル
中には、「机の引き出しに入れていたバッテリーが膨らみ、開けたときに火花が飛んだ」「知らずに金属と一緒に入れていてショートした」など、誤った保管方法によるトラブルの体験談もあります。
また、「高温になる車内に放置していたら、気づいたときにはバッテリーがふくらんでいて怖かった」という声もありました。
ちょっとした油断が大きな事故につながることもあるため、日常的に注意を払うことがとても大切です。
専門家からのアドバイス・推奨ルート
専門家は「異変を感じたら使わず、安全な場所に保管し、すぐに回収依頼を」「自己判断で分解や破棄をするのは絶対にNG」と警鐘を鳴らしています。
推奨されるルートとしては、①絶縁処理をする → ②自治体や回収店のルールを確認 → ③店舗や業者へ持ち込む、という流れです。
また、「保証書や製品情報を保管しておくことで、メーカー対応が受けやすくなる」といった実用的なアドバイスもありました。
よくある質問Q&A

Q1: 中の液体が漏れてるけど触って大丈夫?
絶対に素手で触ってはいけません。
漏れ出た液体は強い腐食性を持ち、皮膚に炎症を起こしたり、目や粘膜に入ると深刻なダメージを与える可能性があります。
やけどやかぶれを引き起こすこともあり、特に小さなお子さんやペットがいるご家庭では要注意です。
対処する際は、厚手のゴム手袋やマスク、保護メガネなどを着用し、液体に直接触れないよう注意しましょう。
そのままの状態で放置せず、すぐに密閉できる袋などに入れて、安全な場所で保管してください。
作業後は必ず石けんで手を洗い、皮膚に異常があればすぐに医療機関を受診しましょう。
Q2: 車に置いてたら膨張した!保証はきく?
多くのメーカーでは「高温環境下での使用・保管」は保証対象外とされています。
特に夏場の車内は70℃を超えることもあり、モバイルバッテリーにとっては過酷な環境です。
そのため、車内放置による膨張や変形は自然故障とは認められない可能性が高く、保証対象外となる場合がほとんどです。
ただし、購入から間もない時期に膨張が発生した場合や、明らかに製造上の不具合と思われる場合は、初期不良として対応してもらえることもあります。
保証書の記載内容をよく確認したうえで、購入店舗やメーカーのサポート窓口に相談してみるとよいでしょう。
Q3: 外箱がない場合、回収してもらえる?
多くの回収業者や家電量販店では、外箱がなくても本体があれば回収可能です。
バッテリー自体に製品名や型番、メーカー名などが記載されていることが多く、それを確認できればスムーズに回収してもらえることがほとんどです。
ただし、製品の種類や状態によっては、安全上の理由で受付を断られるケースもあります。
特に液漏れや破損がひどい場合には、事前に電話やメールなどで問い合わせておくと安心です。
保証書やレシートがあれば持参し、回収の際に提示できるようにしておくとさらにスムーズです。
チェックリスト|処分前にやるべき3つのこと
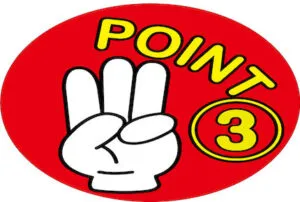
■ 保証・回収サービスの有無を確認
購入時のレシートや保証書を確認し、製品が無償交換やメーカー回収の対象になっていないかを調べましょう。
特に保証期間内であれば、交換対応してもらえるケースもあります。
■ 絶縁処理・保管場所の見直し
端子を電気を通さない絶縁テープでしっかり覆い、高温・多湿を避けた冷暗所で保管しましょう。
火の近くや直射日光が当たる場所、車内などは避けることが鉄則です。耐熱容器や金属缶に入れておくとより安心です。
■ 自治体または業者の対応ルール確認
お住まいの自治体や利用予定の業者の公式サイトをチェックし、回収方法や受付時間、必要な手続きなどを事前に把握しておきましょう。
自治体によっては回収対象品目や曜日が異なるため、最新情報の確認が重要です。
まとめ|安全&エコに処分するために
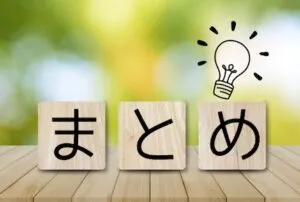
今すぐできる対応まとめ
- モバイルバッテリーが膨張・発熱・液漏れなどの異常を示したら、すぐに使用を中止する
- 絶縁処理を丁寧に行い、安全な場所で一時保管する
- 自治体のルールや回収業者の案内を確認し、正しく処分する
誰でもすぐにできるこれらの対応を実践することで、自分や家族、周囲の人を守ることにつながります。
安心・安全・環境への配慮が大切
モバイルバッテリーの処分は、ただの「ゴミ捨て」とは違います。
正しい処分をすることで、火災や事故のリスクを減らすだけでなく、限りある資源の再利用にも貢献できます。
環境保全やSDGs(持続可能な開発目標)といった社会的な取り組みの一環としても、バッテリーの正しい処分はとても重要なアクションです。
一人ひとりの行動が、よりよい未来につながっていきます。
次回モバイルバッテリーを選ぶときのポイント
- PSEマーク付きなど、国内の安全基準を満たした信頼性のある製品を選ぶ
- 過充電防止・温度管理・ショート防止などの安全機能がついたモデルを選ぶ
- 保証がしっかりしているメーカー品を選び、サポート体制を確認する
- 説明書や保証書は捨てずに保管しておき、いざというときに備える
使用頻度や保管場所に合った容量やサイズを選ぶこともポイントです。
これらのポイントを意識することで、より安全に・より長く安心してモバイルバッテリーを使用することができます。
<PR>
やっぱりエコでしょ!
寿命10倍、なんと5,000回の使用回数。
安全性も高い!世界初のナトリウムイオン電池を採用!?